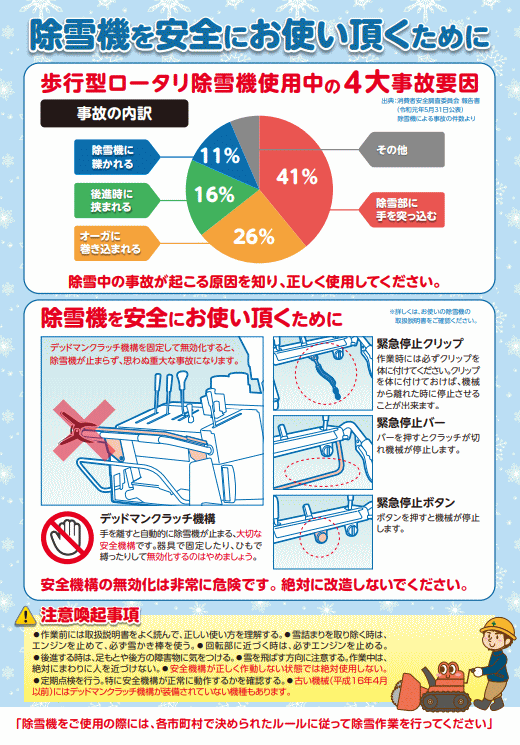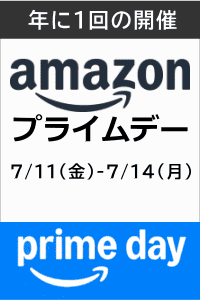大雪の予報などが出た場合の
安全対策・事故例など
平地で雪の降る目安は、上空1500メートル付近の温度がマイナス6℃以下です。また「強い寒気」とは、上空5500メートル付近の温度がマイナス36℃以下の場合で、大雪になる目安とされています。「寒波」は平年に比べ著しく気温が低い寒気が、断続的に流れ込む場合に使われることが多いようです。
[目次]
- 重大事故の恐れがある危険
スリップ事故・車内での一酸化炭素中毒など - 見落としがちなリスク
エアコン室外機の凍結など - 大雪の気象情報
警報・注意報の区分
重大事故の恐れがある危険
道路の凍結によるスリップ・追突事故

都市部では数センチ程度の積雪でも車の追突事故が多発します。普段からスタッドレスタイヤ等を準備している人も少なく、雪道での運転が不慣れなことも原因です。特に橋の上や高架道路は凍結しやすく、雪も溶けにくい状態が続きます。
- 凍結した坂道の上りでは、途中から前へ進めなくなり、後続車とぶつかる事故が目立ちます。下りではハンドル操作やブレーキの制御が困難になり、人身や物損事故につながります。
- 日陰の場所だけ凍結している場合は気づきにくく、路面の状態を慎重に確認する必要があります。坂道などでは前進できずに後続車に逆突する事故も発生しています。
- 通行止めなど交通規制の箇所も多くなります。交通情報に注意して、時間に余裕をもった運転が必要です。
- ご自身が気をつけていても「もらい事故」が多くなります。坂道での逆突などにも注意が必要です。
- 屋根のない屋外駐車場では特に注意!特にコインパーキングの駐車では、積雪よりスリップして動けなったり、駐車場内での走行が困難になる場合、出入り口ゲートのトラブルが発生することもあります。また管理会社の対応が遅れるケースもあるようです。
雪や事故による渋滞・立ち往生
2018年2月の『北陸豪雪』では「北陸自動車道」が通行止になった影響から、福井県と石川県の国道8号線(一部区間)で、3日~4日間の大規模な車の立ち往生が発生しました。大雪や吹雪の恐れがある道路の通行を予定される時は、タイヤチェーンの準備と立ち往生に遭遇した場合の備えが必要です。
- 非常食や飲料水
- 簡易トイレ
- 防寒具、カイロ、生理用品
- スマホの充電器・予備バッテリー
- 除雪用のスコップ
- タイヤが雪に埋もれた場合に、牽引するためのロープ、タイヤの下に敷くネットなど
雪の日に車内での仮眠は危険!

エンジンをかけた状態でマフラー(排気口)が雪で覆われてしまうと、排気ガスが車内に入り込み、一酸化炭素中毒を起こす場合があります。
雪が降っている道路、雪が積もりそうな場所で、エンジンをかけたまま停車した車内に長時間いることは大変危険です。立ち往生で救助を待つ間の死亡事故も発生しています。
やむを得ない場合は、定期的にマフラー付近の除雪を行いましょう。ただし大雪の場合は短時間で再び雪に埋もれることもあり、仮眠などは危険です。マフラーや排気ガスの熱で降り積もる雪を溶かすことは出来ません。また長時間同じ姿勢でいるとエコノミークラス症候群(下半身の血行不良で血栓が発生)のおそれもあります。定期的に体を動かすことも必要です。
JAFによると車が雪に埋もれた状態でエンジンをかけると、車内の一酸化炭素(※)濃度は22分で検知器の上限値に達し、約3時間で死亡する危険があるということです。(窓を5センチほど開けた場合も40分で上限値に到達)また車庫など換気の悪い場所で、エンジンをかけたままの車内でも同様の事故の恐れがあります。※一酸化炭素は空気とほぼ同じ重さ(わずかに軽い)のため、空気中を漂います。無色無臭であり気づきにくい事故です。
停電などのため車内で暖をとる場合も注意が必要です。また小型発電機を利用する場合は、周辺に一酸化炭素を排出する場合もあり屋内では使用せず、屋外においても周囲に近づかないようにしましょう。
歩行者の転倒事故

歩行中の転倒事故も目立ちます。特に階段や坂道、道路上のマンホールや側溝のフタ(金属)の上は滑りやすくなっています。転んだことでケガをしたりスマホなどを破損してしまうこともあります。また歩道橋も注意が必要です。
- 雪道を歩くときは、靴底全体を路面につけ小幅でゆっくりと歩くことで、滑って転ぶことが少なくなります。歩道橋などの階段では手すりを使いましょう。
- 滑りにくい靴を履きましょう。
- 横断歩道の白線は凍っていることに気づきにくいため注意が必要です。
- 手をポケットなどに入れたまま歩くのは、転んだ時に大けがの原因になります。
- ご高齢の方は、出来るだけ外出を控えましょう。
- 雪道を歩いたあとで、ビルや店に入る場合には、靴底の雪をしっかり落としましょう。濡れたままでは、滑りやすく危険です。
見落としがちな危険・リスク
自動車のバッテリーあがり
温度が低いほどバッテリーの化学反応は遅くなり、電圧が下がるのが早くなります。最近はカーナビや車載カメラなど、電源を必要とする装備も増え負荷が大きくなっています。
普段買い物などで短い距離しか走らない場合は、寿命が短くなることもあります。バッテリー液の確認だけでなく、定期的にガソリンスタンドや整備工場での点検が大切です。(劣化具合の判断は素人では困難なことも)
ディーゼル車(軽油)の燃料詰まり
ディーゼル車で使われる軽油は、気温が低いと固まる性質があります。寒冷地以外では2号軽油が多く使われ、気温がマイナス5℃以下になると固まり始めます。寒冷地に行く場合は、目的地のガソリンスタンドで給油をおすすめします。
水道管の凍結
- 屋外の水道管では、気温がマイナス4℃くらいから凍結が始まります。蛇口部分の凍結防止には、タオルなどを巻くだけで効果があります。
- 水道管が凍結したらお湯で温めます。(熱湯は避ける。配水管などにダメージを与える場合があります)
事故・トラブル
(1)子どもの事故
氷の張った池などでは、子供たちがはしゃぐこともあります。氷の上に乗った場合、割れて水に落ちる危険があります。十分な注意が必要です。2020年冬には死亡事故も発生しています。
(2)屋根からの落雪や落氷
雪の少ない地域では、屋根などに積もった雪が晴れてくるとすぐに溶け出します。普段は頭上を気にすることがないため、注意が必要です。
最近では家の屋根に設置したソーラーパネルから積もった雪が落ち、ケガをする事故も発生しています。
(3)屋外配線(架空線)の断線
自宅の敷地内で離れた建物と電話線などをつないでいる場合(架空線)。線の上に雪が積もると接続部で断線する場合があります。
(4)防犯カメラの結露、レンズの曇り
防犯などで屋外に監視カメラを設置している住宅、店舗も多いと思います。カメラ内部の結露などで、動作不良やレンズの曇りが発生して、防犯上の支障が出る場合があります。
(5)赤外線センサーの雪対策
防犯用の赤外線センサーについても、センサー部が雪に覆われ正常な動作に支障が出る場合もあります。センサー部に雪が覆われないように、カバーなどで囲う対策も必要です。
(6)エアコン室外機の雪対策
エアコンの室外機は雪や低温に弱く、雪に覆われたり内部が結露した場合、安全装置が働いて暖房が停止する場合があります。大雪が予想される場合、室外機が雪に覆われないようにする対策が必要です。
(7)観葉植物、鑑賞魚、ペットの対策
観葉植物も種類によっては、寒さに弱くダメージを受けてしまいます。また金魚などの鑑賞魚を飼う水槽の温度、犬や猫、小鳥などペットへの配慮も必要です。毛の短い犬、小型犬は寒さに弱いため配慮が必要です。
除雪作業・除雪機による事故

除雪作業中の事故が目立っています。除雪作業はできるだけ2人以上で行い、雪下ろしにあたっては屋根からの転落にも注意が必要です。また作業中は携帯電話を所持することで、もしも雪に埋まった場合には、架電することで着信音による早期発見につながります。
おもな事故原因(消費者庁による調査)
- 除雪部に手を突っ込む:41%
- 除雪部に巻き込まれる:26%
- 壁などの挟まれる:16%
- 除雪機にひかれる:11%
特に歩行型ロータリー除雪機の安全装置を無効化した状態での使用で、事故が目立つということです。(作業を楽にするために、安全装置であるデッドマンクラッチをひもで縛るなどで固定することは、絶対に行わないこと)また雪に隠れた障害物で転倒する事故にも注意が必要です。
印刷して除雪機の保管場所などに掲示すれば、事故防止が期待できそうです。
「消費者庁」が公開している除雪機による事故防止ビデオ(3分57秒)です。除雪機の操作はチョットした油断が重大な事故につながります。視聴をおすすめします。また作業時には子どもを近づけないことも大切です。
大雪警報・注意報について
大雪特別警報
積雪深が50年に1度の値以上となった地域が府県程度の広がりの範囲に出現し、さらに警報級の降雪が丸1日程度以上続くと予想される場合。(気象庁の基準)
大雪警報
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。(気象庁の基準)
大雪警報の基準(関東・東海)[表示]
平成28年11月17日から、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県で、大雪警報の発令基準が変更になっています。
変更後の基準は、下記のとおりです。
12時間降雪の深さ10cm (平地の主要道路等で除雪を開始する等の積雪深)
※変更前は、24時間降雪の深さ 20~30cm
大雪注意報
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表。