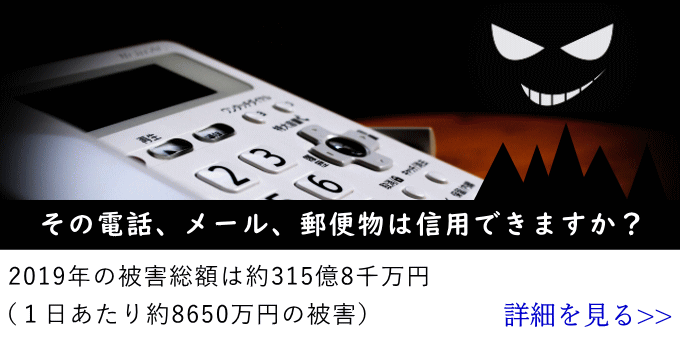被害総額はもっとも大きかった2014年(約556億円)をピークに、減少傾向は続いているものの2019年でも300億円を超えています。また認知件数は高水準で横ばいが続いています。
[目次]
- 被害に遭いやすい人
・10個の診断項目 - 詐欺被害に遭わないために
・確証バイアスに陥らない
2019年の被害総額は315億8千万円
オレオレ詐欺、架空請求など手口も多様かつ巧妙化しており、警察や自治体による全国的な対策、啓発活動も進んでいます。しかし何よりも、不審な電話や郵便、勧誘に対して「常に注意する意識」を高めることが大切です。ご高齢の方には、家族や周囲の方々の協力も不可欠です。
詐欺被害に遭いやすい人
下記の項目で、騙されやすいタイプかご自分で診断できます。
(NHKで特集された診断項目から引用)
- 火災保険や生命保険の契約金額を知らない
- 車や部屋の合鍵を持っていない
- テレビをあまり見ない
- ひまがあれば、本や雑誌を読みたいタイプだ
- 大事なことは、いつも自分で決める
- こだわりが強いタイプだと思う
- 占いや風水を信じるタイプだ
- UFOはきっといると信じている
- 開運グッズを3つ以上持っている
- 流行に流されやすいタイプである
診断結果について
- 1~3個の項目に当てはまる方は、リスクに対する意識や詐欺への注意が低い傾向があります。
- 4~6個の項目に当てはまる方は、自信過剰な傾向です。
- 7~10個の項目に当てはまる方は、人が良すぎるタイプである傾向です。
チェック項目のうち、4つ以上に当てはまる方は、詐欺などの被害に遭いやすいと診断されています。また下記の項目に当てはまる人も騙されやすい傾向にあるそうです。(社会心理学者の西田公昭氏による)
- 自分は大丈夫と思っている
- 非科学的思考の持ち主
- ストレスや不安定な状態に弱い
- 権威に弱い
- 誰に対しても嫌われないようにする
- 集団に影響されやすい
被害者の9割以上は騙されないと思っていた
「宮城県警生活安全企画課」が実施した調査によると、被害者の92%が「特殊詐欺の被害に遭わない自信があった」と回答しています。詐欺の被害は「私のところに詐欺師は来ないし、詐欺なら見破れる」との思い込みが原因になっていると、調査結果から推察できます。
“人の話を疑ってかかる”というのは、あまり気持ちの良いものではありません。しかし疑うことや話の裏(確認をとる)も考えながら、自己防衛することが被害に遭わないために必要な時代です。詐欺事件でもカモリストと呼ばれ、過去に被害にあった方(騙されたことのある人)の名簿を利用して、ターゲットにするケースも少なくありません。
人が意思や行動を決定する要素には、「直感的な判断」と「熟慮の上での判断」という2つがあります。例えば詐欺師によって、身内が緊急事態だと聞かされると、判断までの時間が短い「直感」に傾き、冷静な判断を奪われてしまいます。詐欺師はこの「直感的な判断」を利用して、不安を煽り、その解決策を提示するなどして、相手の心に揺さぶりをかけ、理性的な判断(熟慮の上での判断)を困難な状態にします。
「直感的判断」で自分が正しいと思い込んだり、スグに解決しようと行動を起こしてしまうと、自分に都合のいい話ばかりを求め、不自然な点があっても気づかない、または無視してしまうようになります。
また自己の先入観を補強する「確証バイアス」と言われる心理に陥ってしまいます。結果として詐欺師の描いた筋書き通りに操られ、被害を出す結果につながります。また騙されたとは信じたくない心理も働くため、他者のアドバイスや指摘を受け入れにくくなり、被害を拡大するケースもあります。
詐欺被害に遭わないために
絶対に慌てないこと!
詐欺師たちは、電話やメール、郵便などあらゆる手段を使い、騙せる相手を探しています。そしてターゲットを見つけたら、巧妙な演出で相手を慌てさせ、正常な判断をさせないようにします。特に「劇場型」と呼ばれる詐欺では、複数の人が連携して演出し信じ込ませます。
普段は冷静な人でも、身内が事件や事故に巻き込まれたなどの“非日常的な状況”におかれると動揺しがちです。“もしかしたら詐欺?ウソの話しかも?”と自分に言い聞かせることで、慌てないことを事前に心に止めておくことが必要です。
少しでも不審や不自然さを感じたら、その場で家族や友人、警察などに相談します。すぐに相談することがポイントです。時間を置いてしまうと、自分に都合のいい理由を考えてしまい、手遅れになることも少なくありません。110番がしにくい場合は、#9110(全国共通)で、警察の相談窓口につながります。
特殊詐欺で多く見られる親族や公的機関、警察などを装った手口は、相手を油断させることが目的です。また不安や心配する心理を利用して、慌てさせる(または煽る)ことで詐欺師の描いたストーリーで騙そうとしています。
人を外見や表情、声で判断しない
持ち物も演出のひとつかも?
人は初対面の人の印象を3秒で判断するといわれます。服装や表情、声などで過去の経験則から判断しがちです。点検商法などで作業服を来た人が勧誘するのは、多くの人が持つ先入観を利用して信じ込ませるためです。
また電話においても、詐欺師たちは相手によって、立場や声(話し方)を変え、信じ込ませようとします。
- 作業服を着ているから職人さんとは限らない。
- 名刺や名札、バッチや証明書は簡単に偽造できます。
パンフレットや資料も詐欺ツール
おしゃれなカタログ、分厚い資料などを見せられると、「有名な企業かもしれない」、「信用がありそうだ」と想像しがちです。しかし架空のカタログや資料などは、簡単に作れてしまう時代です。ホームページなども同じです。外見に惑わされて間違った判断をしないことも大切です。
はっきり断る意思が必要
少しでも不安や不審を感じたら、即断せずにはっきり断る意思(態度)が必要です。詐欺師たちは断られないように、さまざまな演出で騙そうとします。不審な電話などは長い会話をせずに、スグに切ることが大切です。電話を切る前に、相手を気遣うような言葉は要りません。詐欺師たちは、電話に出た人との会話から感じる人柄で、騙せる人であるかを判断しています。
詐欺師たちに柔らかな断り方をしたりすると、「この人は人が良さそうだから、何度かアプローチすれば、騙せるかもしれない」と考え、何度もアプローチしてくる場合があります。
詐欺にも危険予知訓練(KYT)を!
工場や製造などの現場で働く方は、事故や災害を未然に防ぐことを目的に、KYT(Kiken Yochi Training)を実施していることが多いと思います。KYTは、作業手順のマニュアル整備、作業時の声出しや指差し、危険の予想などを行うものです。詐欺被害対策においても同様で、常に詐欺に遭うかもしれないと考え、情報収集や防衛意識を高めることが必要です。
- 家族や地域において、定期的に声を掛け合う。
- 詐欺防止の啓発ポスターなどを常に見える場所に貼る。
- 地域の相談窓口、電話番号などを電話機の近くに貼る。(#9110など)
- 電話は非通知拒否にして、知らない人からの電話には出ない。(固定電話は常に留守番にすることも効果的)
- NTTの電話帳(ハローページ)への電話番号記載を拒否する。
- 信頼のおけない相手の懸賞やアンケートへの個人情報の記入は行わない。
詐欺師たちに、あきらめさせる工夫を!
詐欺被害はご高齢の方に多く、社会経験や知識が豊富であるはずの世代が騙されています。詐欺師達はあらゆる演出を使いながら、相手のプライドや欲望、不安になる心理、心配する気持ちなどを利用しています。
- この人は騙せそうにないな。手ごわい人だ。
- これ以上の話しをすると(相手にしたら)警察に捕まるな。
- 「騙されたふり作戦」かも知れない。
- 在宅時も常に留守番電話にしておく。
昨今では「手渡し型詐欺」も増加しています。自宅へ受け取りにくるケースや悪質な訪問販売を防ぐためにも、可能であれば、監視カメラの設置も抑止効果が期待できます。また空き巣などの防犯対策にもなります。
また詐欺犯は声の証拠を残すことを嫌がるため、在宅時でも常に留守番電話に設定し、残されたメッセージを聞いて相手を確認してからかけ直すのも効果的です。
固定電話機においては、ナンバーディスプレイの利用や留守番電話の利用も効果的です。また郵便物(日本郵便株式会社)では、紙に「受取拒絶」と書き、押印または署名をして郵便物に貼り付け、郵便局に持って行くかポストに投函することで郵便物は差出人に返送されます。この場合の郵便料金は、差出人の負担になるため、リストから外されることも期待できます。※受け取り拒否ができるのは開封前(通常はがきなどを除く)に限られ、受取人本人(名宛人)のみです。
騙されなかった人の行動
北海道警察の資料では、実際に騙されなかった人の行動が分析されています。
- 事前の情報収集
- 家族間の意識の共有
- 不審電話への冷静な対応
被害を未然に防いだ女性の話しでは、「おれおれ」・「架空請求」・「還付金」・・・など普段から新聞やテレビ、知人との会話で特殊詐欺の手口や決まり文句などの情報を共有し、不審な電話に対する心の備えを行っていたということです。